| 花や緑、農漁産物などが登場する噺(=落語)の世界を紹介するコーナーです。
第9回は落語に出てくる小噺をひとつ。
――暑さの盛り、甘酒売りの売り声・・・。
甘酒売り「えぇー甘酒ぇー、甘酒ぇー」
男A「おうっ、甘酒屋!」
甘酒売り 「へい、毎度」
男A「あついかい?」
甘酒売り「へい、お熱うございます」
男A「だったら日陰を歩きねぇ」
――と、笑いながら去って行く男。
甘酒売り「なんだい奴ぁ、買わねぇくせに人をからかいやがって。おもしろくもねえ・・・・えぇー甘酒ぇー甘酒ぇー」
――再び商いを始める甘酒売り。これを端で見ていた少々間の抜けた男B。
自分も真似して甘酒売りをおちょくってやろうと考えました。
甘酒売り「えぇー甘酒ぇー、甘酒ぇー」
男B「おうっ甘酒屋!」
甘酒売り「へい、毎度」
男B「あついかい?」
甘酒売り「へい、丁度飲み頃でござい」
男B「うっうっ、そ、そぉーかい。じゃあ、一杯くんな」
――物真似の悪巧みは上手くいくわけもなく、売り子さんも二度も同じ手は食わない。一杯食わされた(飲まされた)のは間抜けな男の方だったようです。
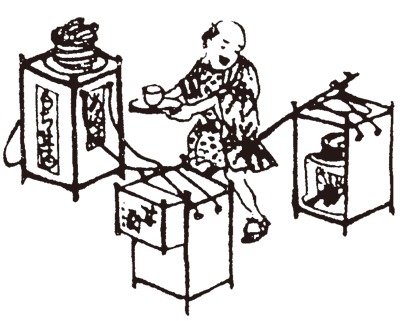 |
このイラストは江戸時代後期に発行された喜田川守貞による『近世風俗志=守貞漫稿(前35巻)』に描かれた江戸時代の甘酒売りの様子。天秤棒の前に茶碗やお盆を、後ろの箱には甘酒を温めるため炭火を熾した炉に釜を据えて売り歩きました。
こうした姿から、一方が熱くてもう一方が冷めている状態を「甘酒屋の荷」と称して「片思い」を連想させる洒落た喩え言葉も生まれました。 |
今回の小噺から分かるように、冬の飲み物として馴染みのあった甘酒は、江戸時代には通年飲まれるようになり、特に気温が上がる夏になると、町中には多くの甘酒売りの声が響いていたそうです。
それというのも甘酒には、暑さにバテて衰えた体力を復活させるためのブドウ糖・ビタミン類・アミノ酸類が多く含まれ、「栄養ドリンク」として、現代の点滴のような役割を担っていたからなのです。平均寿命が50歳にも満たなかった当時の人々にとって、逃れようのない厳しい暑さは大敵でした。食中毒や蚊を媒介とする伝染病などによって夏の死亡率は高く、「夏を越える」ことは大変だったのです。幕府もその効能を十分承知していて低所得者層の健康管理のため、甘酒一杯の販売価格に上限を設定していたそうです。
温めた甘酒(冷やしも有り)は、スイカや瓜などの水菓子や心太、麦湯、冷や水売りなど他の暑気払いの飲食と共に盛んに売られていました。俳句の世界でも甘酒は夏の季語になっています。
|
明治初期に撮影された風俗写真の中の甘酒売り。
体力勝負の車夫(?)が甘酒を飲んで栄養補給中。
【探検コム】歴史画像アーカイブ・データベースより |
| 甘酒は酒同様、水に浸して柔かくした生米を口の中で咀嚼して唾液と混ぜて澱粉を糖化、発酵させたものがルーツとされています。古代中国の王朝では「醴(=甘酒)」を作る専門の官職があったことが伝えられています。 |
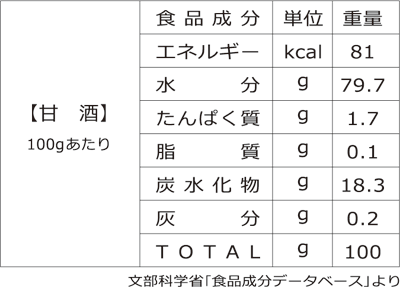 |
|
