 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
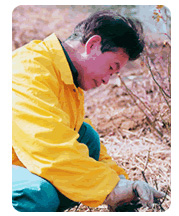 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
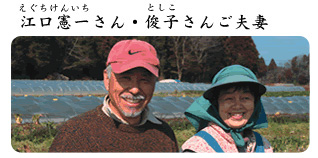
|
|
|||||||||||||||||||||||||||

|
|
|||||||||||||||||||||||||||
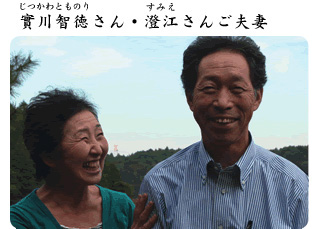 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
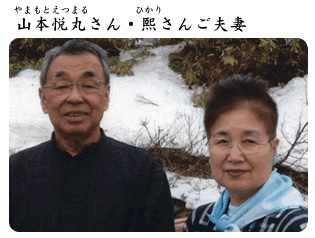 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
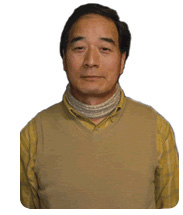 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
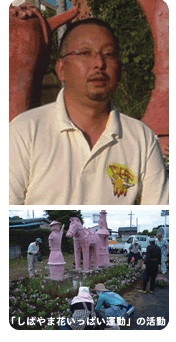 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| [花祭り本舗]の花寿司は成田山新勝寺の参道店舗での販売が有名ですが、全国各地で行われるお祭りやイベント、デパートの物産展へも奥様の久子さんと一緒に出掛けては、実演販売をしたり、自治体に招かれた実技指導なども無償で引き受けています。目の前できれいな花の絵柄や、TVアニメでおなじみのキャラクターの顔が描かれた巻き寿司が出来上がってゆく様子はとても楽しく大好評です。「見た目重視」的な印象の強い花寿司ですが、とんでもない!食べても美味しくなければ、本当の花寿司とはいえません。是非ご賞味あれ。 * * * * * [花寿司・祭り寿司 花祭り本舗] TEL 0479-77-2079 山武郡芝山町新井田324 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
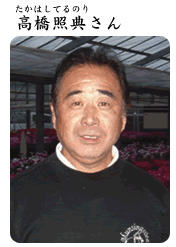 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
至高のシクラメンのほか、オリジナルのアジサイやカーネーションなどは、(有)大栄花園が直営する[花工房
四季彩]でも販売されています。 花工房 四季彩 千葉県成田市前林987-1 TEL/FAX.0476-73-6030 http://www.hana-shikisai.net/ |
 |
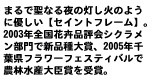 |
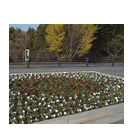 |
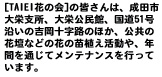 |
||||||||||||||||||||||||
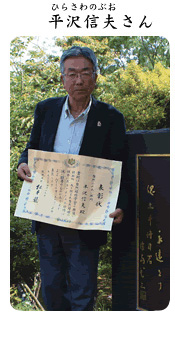 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
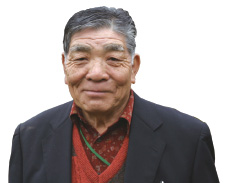 |
|
||
 |
花の会野田主催の園芸教室が開催されました。 2月22日(水)会場は成田天神峰にある花の農場内のガラス温室。午前中に成田山参詣と昼食を終えた花の会野田の会員さん12名に加えて、公募に応じた25名の皆さんが参加されました。農場見学の後、今回の寄せ植えは直径30cmほどのプランターに、プリムラ・ポリアンサス、メラコイデス、デージーの他にポピー、ネモフィラ、アリッサム、ノースポールの中からお好みの2種を選び、合計5株の花でオリジナルの寄せ植え作りを行いました。講師は(農)花の生産舎組合のスタッフの寺本千波さんが務めました。 |
 |
|
 
|
1948年(昭和23年)11月20日、千葉県芝山町の農家(米・野菜・家畜) の長男として生まれた吉川さんは、高校卒業後、地元の丸朝園芸農業協同組合の組合員として米や野菜の生産に従事されました。現在は兼業農家。ふたりのお子様も独立し、愛妻みつ子さんとのふたり暮らし。休日に訪ねてくる5人のお孫さん(すべて男の子! ) と野山を駆ける好々爺ぶりを発揮されています。 当財団の故土井脩司元理事長とは地域の行事を通して知り合い、意気投合。土井さんが「私の弟分」と呼ぶほどに強い信頼を寄せたおひとりでした。1994年(平成6年) には地元有志らと[山中花の会]を発足させ、地域に花の輪を広げていく活動を開始されました。 2001年(平成13年)、当財団が環境事業団の助成金で温室を建てた際にも多大なご助力を頂きました。現在温室では水稲の育苗管理をする他、吉川さんが自ら種を蒔き、育てた花がいっぱいです。その花は春夏秋冬、吉川さんが町内の花壇などに植えて管理、散策中に温室で咲いている色とりどりの花に興味を持ち、話し掛けてくる方には無償で差し上げることもあるそうです。 また、当財団が毎年子供たちと行っている田植え・稲刈り体験の際には、苗床や田んぼの管理をはじめ、全面的なご協力を頂いています。 体験当日には子供たちのためにザリガニやドジョウを獲って下さったり、自ら育てたお花の苗をプレゼントして頂いたり、[花と緑と農芸の里]の様々な活動に欠くことの出来ない頼りになる地元支援者です。 吉川さんは「お年寄りと若い人とは花に対する関心の度合いが違うように感じる。昔はどの家でも庭先に四季折々花が咲いていたし、自分たちで種を採り、慈しみ育てていたように思う。」と、ゆとりを失った当節を嘆く一方で、「花をきっかけに沢山の人たちと交流できる機会を増やすために、これからも花を育て続け、花の輪・人の輪(和)を広げていきたい」と語って下さいました。 |